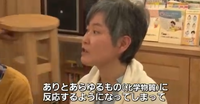› オーナーシェフのブログ › 僕はなぜ与那国島に住んでいるのか 3 「テントサバイバル編」
› オーナーシェフのブログ › 僕はなぜ与那国島に住んでいるのか 3 「テントサバイバル編」2011年10月30日
僕はなぜ与那国島に住んでいるのか 3 「テントサバイバル編」
「テントサバイバル編」
あの夜から、僕たちふたりは与那国島で一緒に生活するようになりました。
世界一周はどうなったのでしょうか。
送別会を開いたりしてくれたみなさま、申し訳ない。
あれからふたりで台湾には行きましたが、僕の海外経験は今のところそれだけです。
偉そうにかなりストイックな思いを込めていたつもりが、やさしさの前にあっけなく陥落してしまいました。
北風よりも太陽に弱いんですね、人間は。
それから少しばかり波乱もありました。
与那国島に住むようになってから、僕はまた波照間島と同じ失敗をしてしまいました。
所持金数千円、銀行がなくてお金がおろせなくなっていたのです。
またも「土木作業員募集」的な張り紙を探して見ましたが、残念ながら与那国島にはそういった都合のいい仕事はありませんでした。
飛び込みで、工事現場などに仕事ありませんか?とお願いしに行くも断られる日々。
彼女は寮で生活していたので、転がり込むわけにもいきませんでした。
祖納で泊まっていた宿のヘルパーさんがテントを持っていたのでお願いして借りに行き、僕は久部良のナーマ浜でテント生活に入ったのです。
風が少し避けられて、人目につきにくい、少し小高くなったところがあり、そこは金比羅様の建つ下あたりです。
小学校のときからテントを張ったりしていたし、高校時代は山岳部の部長もして、単独で登山もしていたのでそんな生活に苦はありませんでした。
何より、愛があった。
しかし、お金もなく全くの無職だったので、僕は自給自足の生活を当面の目標にしました。
魚を釣ったり、貝を拾ったり、銛をもって海辺をウロウロしてると、たまにヒラメやいらぶちゃーなど大物がとれたりすることもありました。
食べられる雑草があると聞けば海水で茹でてみたり、石垣島から持ってきていた米などの食料もあったので、毎日焚き火で自炊したり、雨が降っても薪が濡れないように小屋を作ったり。
漂着するゴミでイスやテーブルや棚を作ったり、なんかそれはそれで楽しかった思い出です。
基本的に飢えていましたが、彼女がこっそり持ってくる食べ物に感謝しつつも、なんかギリギリのところで死なないように飼育されてたのかもしれません。
女は男をコントロールする生き物かもしれない、と、今書きながら思ってみたりします。
4月の与那国島は太陽の光も強烈になってきていて、熱のこもったテントの中のろうそくがぐにゃりと曲がるような日もあり、じりじりと焼かれるような暑さになってきていました。
暑くてしょっちゅう海に入るものだから、いちいち服を着てるのもめんどくさくなってきて、テント生活の数日後には上半身裸の裸族になっていました。
仕事もせず、暇はわりとあったので、僕はあるひとつの作戦を実行することにしました。
それは「ナーマ浜クリンアップ大作戦」です。
このビーチは海流の影響かたくさんのゴミが打ち上げられています。
それら全てを駐車場のあるところまで人力で運ぼう、という計画でした。
ただテントを張り続けて狩猟生活をしていると、何かあやしいやつだと思われてしまうので、少し良い事をしてみようという下心も正直ありました。
その頃は意味も無くポジティブなメンタリティーだったので人目はあまり気にしていませんでした。
それで突如ナーマ浜に現れた、テント生活者のあやしさが払拭されたかどうかは、今思い起こし、考えてみても甚だ疑問が残ります。
最初は流木やブイ、漁網の切れ端などをひきずりながらひとつひとつ運んでいました。
とりあえず駐車場に近い方は、単純な人力でこなしていきましたが、ビーチの奥になるにつれ限界を感じていた僕は工夫を加えていきます。
ゴミの運び方を変えてみることにしました、最初の進化は流れ付いていたベニヤいたに穴を開けて太めのロープを通しその上にゴミを載せて腰でロープを引きながらソリのようにして運んでいくことでした。
炎天下の中、真っ黒に日焼けした裸族がゴミを引っ張っている光景は島の人からみたら異様な姿だったかもしれません。
それでもビーチの端から端までは200メートル以上あったので次第に身体がきつくなって来ました。
次に、考えた方法は浜に流れてついていたプラスチックのパレット、フォークリフトで物を運ぶときに載せている台を活用することです。
そのプラスチックのパレットにプラスチックのブイ(漁業でつかう浮き玉)を10個くらいを結びつけて、海に浮かべたそのイカダの上にゴミを載せて運ぶ方法です。
最終的にイカダ方式で作業効率は格段に上がり、2週間ほどでナーマ浜はゴミ一つない綺麗なビーチへと生まれ変わりました。
その集められたゴミは後に与那国町が回収し、大型ダンプ3台分だったと教えてもらいましたが、チリも積もれば人力でも山になることを身をもって体験しました。
そんなふうにしてちょっと変わったかたちで与那国島にデビューしたわけですが、そのゴミ拾いの光景を島の人が目撃するようになっていったようです。
あいかわらず、自給自足の生活を続けている僕が防波堤で釣りをしていると漁から帰って来たうみんちゅが「にいにい、釣れたか」と声をかけてくれるようになりました。
仮に釣れていても「ダメです全然釣れません」と僕はいつも答えます。
すると「これ食え」といって船の上からカツオやマグロを投げてくれるようになってきたのです。
はたまた、漁港の水道を勝手に借りて水汲みなんかをしてたのですが、酒盛りをしているうみんちゅが手招きしてきます。
怒られるのかな、と恐る恐る寄っていくと「一緒に飲んでけ」と言うのです。
その頃は与那国の方言もうちなーぐちも全然わかりませんでした。
標準語も与那国島独特のイントネーションに馴れないとわかりずらいのですが「おまえがゴミを拾っているのはみんながみてる、与那国町には感謝状を出させるし、困ったことがあればなんでも言え」とうみんちゅ達は言ってくれました。
感謝状の件はうやむやになって未だにもらっていませんが、僕のしらないところで、裸族のあやしいやつから「まいふなー」(おりこうさんという意味)に格上げされてきたようで嬉しく思いました。
世界一周という旅の目的も曖昧になり、その日その日を生きている充実感で満たされていたその当時。
「ちょっとキビ植えするから2~3日バイトしないか」なんて仕事も顔見知りになった人がテントに訪ねて来たりして、わずかながら与那国島テント生活も軌道に乗り始めて来ました。
ゴミ捨て場から拾ってきた鍋やら自作のランプやら、漂着物で作った生活品も増えてきて、雨対策のためテントの下にに砂を盛って基礎を作ったり、いつまでもサバイバル生活を続ける準備は着々と整いつつありました。
そうして、テント生活がひと月と半分を越えた5月の下旬、与那国島に台風がやってきました。
やっぱり砂浜だし台風はすこしきついよね。
などと沖縄の台風を経験したことのない僕は、テント周りに砂の壁をせっせと築きあげていましたが、空が暗くなり雨が降ってきて風がバタバタとテントを揺らしてきたので作業を切り上げて中に避難することにしました。
風と雨は弱まるはずも無くだんだんと強くなり始めた頃、テントにある訪問者がやってきました。
その頃、何回か一緒に飲んだりして知り合いになっていた島のおじーでした。
おじーが言うには「そんなところにテントを張ってたら危ない、空家があるからとりあえずそこに住んどけ、家賃はいらないから」とのことでした。
案内された空家はトタン屋根がボロボロになって雨漏りがして、床も破れところどころ地面がのぞいていました。
それでもテントからブロック積みの住宅に昇格したわけですから、僕にとっては事実上かなりのグレードアップのはずです。
おじーの申し出に感謝しながら、僕は雨の中テントをたたみ、家財道具を移動して、住み慣れたナーマ浜を後にしました。
5月の小型台風は、僕が仙台で経験したどの台風よりも大きく、電気も水道も通っていない廃屋の中で不安な夜を彼女とふたりで過ごしました。
翌日の夕方、台風がおさまってからナーマ浜の旧宅に行ってみると僕がせっせと築いていた砂の壁も土台もかまどもテーブルもイスも全て波がさらっていました。
あの時のおじーの好意に再び感謝すると共に、それからその廃屋でふたりの生活を始めることになります。
住所不定無職のあやしいやつから、とりあえず住所不定の4文字が消えることになったのです。
家というものは人が住むことで、命を与えられます。
住むことで少しづつ命を吹き返していく家は、与那国島に生活の場を移したばかりの僕と彼女にとってかけがえのない家庭の場であったのです。
窓が何箇所かなかったので、バナナの葉っぱを貼り付けたりした住宅はやっぱりあやしげな家に見えたのかもしれません。
でも、そんなことは一向に構いません、いかにそれが貧乏くさくても、何一つ恥ずかしと思ったことはありませんでした。
ふたりで力を合わせて小さな家庭を築き、自立しているという誇りは、黒潮海流の真っただ中にぽつんと現れた孤高の与那国島の断崖絶壁のように気高く屹立していました。
幸い、当時の与那国島には巨大なゴミ捨て場があって、集められた家庭ゴミとともに建築廃材なども野ざらしにされており、質を問わなければ僕のような人間にとって夢のDIYセンターのような存在でした。
ナーマ浜でゴミをせっせと拾っていたあやしい男は、以来このゴミ捨て場によく出没するようになりました。
ベニヤ板を拾い、ハンマーをゴミの山から発掘し廃材をつかって廃屋を修理し始めました。
その後1年あまりしてから、僕は再び思い出のフェリー「よなくに」で石垣島を訪れ銀行に行き、おろしたお金でおじーからこの家を買い取りました。
この家が現在のRistoranteTESUとMoist Chocolat Yonaguni の自宅兼店舗になっています。
僕が料理の世界に足を踏み入れるのはまた少し先の話で、次回「Ristorante編」でその話をしたいと思います。
余談ですが、与那国島の農協でも他銀行のお金がおろせることを島の人から教えてもらったのはそれから何ヶ月か後のことでした。
あの夜から、僕たちふたりは与那国島で一緒に生活するようになりました。
世界一周はどうなったのでしょうか。
送別会を開いたりしてくれたみなさま、申し訳ない。
あれからふたりで台湾には行きましたが、僕の海外経験は今のところそれだけです。
偉そうにかなりストイックな思いを込めていたつもりが、やさしさの前にあっけなく陥落してしまいました。
北風よりも太陽に弱いんですね、人間は。
それから少しばかり波乱もありました。
与那国島に住むようになってから、僕はまた波照間島と同じ失敗をしてしまいました。
所持金数千円、銀行がなくてお金がおろせなくなっていたのです。
またも「土木作業員募集」的な張り紙を探して見ましたが、残念ながら与那国島にはそういった都合のいい仕事はありませんでした。
飛び込みで、工事現場などに仕事ありませんか?とお願いしに行くも断られる日々。
彼女は寮で生活していたので、転がり込むわけにもいきませんでした。
祖納で泊まっていた宿のヘルパーさんがテントを持っていたのでお願いして借りに行き、僕は久部良のナーマ浜でテント生活に入ったのです。
風が少し避けられて、人目につきにくい、少し小高くなったところがあり、そこは金比羅様の建つ下あたりです。
小学校のときからテントを張ったりしていたし、高校時代は山岳部の部長もして、単独で登山もしていたのでそんな生活に苦はありませんでした。
何より、愛があった。
しかし、お金もなく全くの無職だったので、僕は自給自足の生活を当面の目標にしました。
魚を釣ったり、貝を拾ったり、銛をもって海辺をウロウロしてると、たまにヒラメやいらぶちゃーなど大物がとれたりすることもありました。
食べられる雑草があると聞けば海水で茹でてみたり、石垣島から持ってきていた米などの食料もあったので、毎日焚き火で自炊したり、雨が降っても薪が濡れないように小屋を作ったり。
漂着するゴミでイスやテーブルや棚を作ったり、なんかそれはそれで楽しかった思い出です。
基本的に飢えていましたが、彼女がこっそり持ってくる食べ物に感謝しつつも、なんかギリギリのところで死なないように飼育されてたのかもしれません。
女は男をコントロールする生き物かもしれない、と、今書きながら思ってみたりします。
4月の与那国島は太陽の光も強烈になってきていて、熱のこもったテントの中のろうそくがぐにゃりと曲がるような日もあり、じりじりと焼かれるような暑さになってきていました。
暑くてしょっちゅう海に入るものだから、いちいち服を着てるのもめんどくさくなってきて、テント生活の数日後には上半身裸の裸族になっていました。
仕事もせず、暇はわりとあったので、僕はあるひとつの作戦を実行することにしました。
それは「ナーマ浜クリンアップ大作戦」です。
このビーチは海流の影響かたくさんのゴミが打ち上げられています。
それら全てを駐車場のあるところまで人力で運ぼう、という計画でした。
ただテントを張り続けて狩猟生活をしていると、何かあやしいやつだと思われてしまうので、少し良い事をしてみようという下心も正直ありました。
その頃は意味も無くポジティブなメンタリティーだったので人目はあまり気にしていませんでした。
それで突如ナーマ浜に現れた、テント生活者のあやしさが払拭されたかどうかは、今思い起こし、考えてみても甚だ疑問が残ります。
最初は流木やブイ、漁網の切れ端などをひきずりながらひとつひとつ運んでいました。
とりあえず駐車場に近い方は、単純な人力でこなしていきましたが、ビーチの奥になるにつれ限界を感じていた僕は工夫を加えていきます。
ゴミの運び方を変えてみることにしました、最初の進化は流れ付いていたベニヤいたに穴を開けて太めのロープを通しその上にゴミを載せて腰でロープを引きながらソリのようにして運んでいくことでした。
炎天下の中、真っ黒に日焼けした裸族がゴミを引っ張っている光景は島の人からみたら異様な姿だったかもしれません。
それでもビーチの端から端までは200メートル以上あったので次第に身体がきつくなって来ました。
次に、考えた方法は浜に流れてついていたプラスチックのパレット、フォークリフトで物を運ぶときに載せている台を活用することです。
そのプラスチックのパレットにプラスチックのブイ(漁業でつかう浮き玉)を10個くらいを結びつけて、海に浮かべたそのイカダの上にゴミを載せて運ぶ方法です。
最終的にイカダ方式で作業効率は格段に上がり、2週間ほどでナーマ浜はゴミ一つない綺麗なビーチへと生まれ変わりました。
その集められたゴミは後に与那国町が回収し、大型ダンプ3台分だったと教えてもらいましたが、チリも積もれば人力でも山になることを身をもって体験しました。
そんなふうにしてちょっと変わったかたちで与那国島にデビューしたわけですが、そのゴミ拾いの光景を島の人が目撃するようになっていったようです。
あいかわらず、自給自足の生活を続けている僕が防波堤で釣りをしていると漁から帰って来たうみんちゅが「にいにい、釣れたか」と声をかけてくれるようになりました。
仮に釣れていても「ダメです全然釣れません」と僕はいつも答えます。
すると「これ食え」といって船の上からカツオやマグロを投げてくれるようになってきたのです。
はたまた、漁港の水道を勝手に借りて水汲みなんかをしてたのですが、酒盛りをしているうみんちゅが手招きしてきます。
怒られるのかな、と恐る恐る寄っていくと「一緒に飲んでけ」と言うのです。
その頃は与那国の方言もうちなーぐちも全然わかりませんでした。
標準語も与那国島独特のイントネーションに馴れないとわかりずらいのですが「おまえがゴミを拾っているのはみんながみてる、与那国町には感謝状を出させるし、困ったことがあればなんでも言え」とうみんちゅ達は言ってくれました。
感謝状の件はうやむやになって未だにもらっていませんが、僕のしらないところで、裸族のあやしいやつから「まいふなー」(おりこうさんという意味)に格上げされてきたようで嬉しく思いました。
世界一周という旅の目的も曖昧になり、その日その日を生きている充実感で満たされていたその当時。
「ちょっとキビ植えするから2~3日バイトしないか」なんて仕事も顔見知りになった人がテントに訪ねて来たりして、わずかながら与那国島テント生活も軌道に乗り始めて来ました。
ゴミ捨て場から拾ってきた鍋やら自作のランプやら、漂着物で作った生活品も増えてきて、雨対策のためテントの下にに砂を盛って基礎を作ったり、いつまでもサバイバル生活を続ける準備は着々と整いつつありました。
そうして、テント生活がひと月と半分を越えた5月の下旬、与那国島に台風がやってきました。
やっぱり砂浜だし台風はすこしきついよね。
などと沖縄の台風を経験したことのない僕は、テント周りに砂の壁をせっせと築きあげていましたが、空が暗くなり雨が降ってきて風がバタバタとテントを揺らしてきたので作業を切り上げて中に避難することにしました。
風と雨は弱まるはずも無くだんだんと強くなり始めた頃、テントにある訪問者がやってきました。
その頃、何回か一緒に飲んだりして知り合いになっていた島のおじーでした。
おじーが言うには「そんなところにテントを張ってたら危ない、空家があるからとりあえずそこに住んどけ、家賃はいらないから」とのことでした。
案内された空家はトタン屋根がボロボロになって雨漏りがして、床も破れところどころ地面がのぞいていました。
それでもテントからブロック積みの住宅に昇格したわけですから、僕にとっては事実上かなりのグレードアップのはずです。
おじーの申し出に感謝しながら、僕は雨の中テントをたたみ、家財道具を移動して、住み慣れたナーマ浜を後にしました。
5月の小型台風は、僕が仙台で経験したどの台風よりも大きく、電気も水道も通っていない廃屋の中で不安な夜を彼女とふたりで過ごしました。
翌日の夕方、台風がおさまってからナーマ浜の旧宅に行ってみると僕がせっせと築いていた砂の壁も土台もかまどもテーブルもイスも全て波がさらっていました。
あの時のおじーの好意に再び感謝すると共に、それからその廃屋でふたりの生活を始めることになります。
住所不定無職のあやしいやつから、とりあえず住所不定の4文字が消えることになったのです。
家というものは人が住むことで、命を与えられます。
住むことで少しづつ命を吹き返していく家は、与那国島に生活の場を移したばかりの僕と彼女にとってかけがえのない家庭の場であったのです。
窓が何箇所かなかったので、バナナの葉っぱを貼り付けたりした住宅はやっぱりあやしげな家に見えたのかもしれません。
でも、そんなことは一向に構いません、いかにそれが貧乏くさくても、何一つ恥ずかしと思ったことはありませんでした。
ふたりで力を合わせて小さな家庭を築き、自立しているという誇りは、黒潮海流の真っただ中にぽつんと現れた孤高の与那国島の断崖絶壁のように気高く屹立していました。
幸い、当時の与那国島には巨大なゴミ捨て場があって、集められた家庭ゴミとともに建築廃材なども野ざらしにされており、質を問わなければ僕のような人間にとって夢のDIYセンターのような存在でした。
ナーマ浜でゴミをせっせと拾っていたあやしい男は、以来このゴミ捨て場によく出没するようになりました。
ベニヤ板を拾い、ハンマーをゴミの山から発掘し廃材をつかって廃屋を修理し始めました。
その後1年あまりしてから、僕は再び思い出のフェリー「よなくに」で石垣島を訪れ銀行に行き、おろしたお金でおじーからこの家を買い取りました。
この家が現在のRistoranteTESUとMoist Chocolat Yonaguni の自宅兼店舗になっています。
僕が料理の世界に足を踏み入れるのはまた少し先の話で、次回「Ristorante編」でその話をしたいと思います。
余談ですが、与那国島の農協でも他銀行のお金がおろせることを島の人から教えてもらったのはそれから何ヶ月か後のことでした。
Posted by Moist Chocolat at 19:14│Comments(1)
この記事へのコメント
こんにちは
与那国に
行きたくてやっと今年一月に行きました
このブログは行ってから帰って気がつきました
残念です
自分はもう50も半ば
自営業です
昔バックパッカーで
ソビエトからヨーロッパ(イギリスを除く)
を回りました
与那国のブログにひかれ何回か読みなおしました
、来年また行こうかとおもいます
今回はティダンに泊まりました
与那国の雰囲気が気に入ってしまった一人です
与那国に
行きたくてやっと今年一月に行きました
このブログは行ってから帰って気がつきました
残念です
自分はもう50も半ば
自営業です
昔バックパッカーで
ソビエトからヨーロッパ(イギリスを除く)
を回りました
与那国のブログにひかれ何回か読みなおしました
、来年また行こうかとおもいます
今回はティダンに泊まりました
与那国の雰囲気が気に入ってしまった一人です
Posted by ひろし at 2015年09月06日 18:03
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。